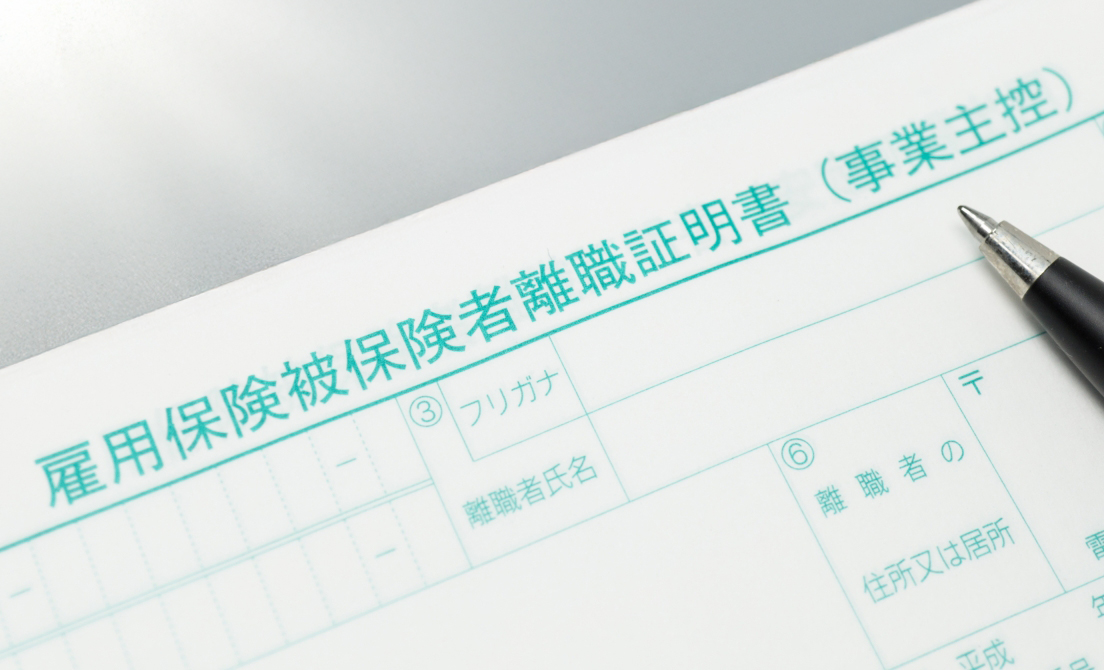従業員の退職時、労務担当者にとって避けて通れないのが離職票の手続きです。離職票は、退職者が失業手当(基本手当)を受け取るために不可欠な重要書類。手続きに不備があると、退職者に不利益が生じ、トラブルに発展する可能性もあります。
今回は、離職票の発行手続きから、書類の具体的な書き方まで、労務担当者が知っておくべきポイントをまとめました。
離職票とは?
正式名称は「雇用保険被保険者離職票」といい、雇用保険に加入していた方がハローワークで失業手当を申請する際に必要な書類です。
離職票は以下の2枚で構成されています。
・離職票-1: 資格喪失の事実を証明する書類。
・離職票-2: 離職日以前の賃金状況や離職理由が記載された書類。
企業がハローワークに提出する段階では「離職証明書」と呼ばれ、ハローワークが公的に証明した後に「離職票」となります。
離職票発行の5つのステップ
ここでは、離職票を発行するまでの流れを5つのステップで解説します。
ステップ1:離職票発行の希望を確認
退職者本人に離職票が必要かどうかを確認します。ただし、離職日時点で59歳以上の場合は、本人の希望にかかわらず発行が必要です。
ステップ2:必要書類を準備し、離職証明書を作成
ハローワークで入手した専用の複写式用紙(事業主控・ハローワーク提出用・離職票-2の3枚綴り)に記入します。賃金状況や離職理由を正確に記載するため、出勤簿(タイムカード)と賃金台帳を準備しましょう。
ステップ3:離職者に確認・署名をしてもらう
作成した離職証明書の内容を離職者本人に確認してもらい、署名をもらいます。特に、離職理由は失業手当の給付日数などに影響するため、必ず事前に合意を取りましょう。
ステップ4:ハローワークに提出
離職日の翌々日から10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届と離職証明書を添えて、管轄のハローワークに提出します。
提出が遅れると、退職者が失業手当の手続きを進められず、不利益を被るため、迅速な手続きが重要です。
ステップ5:離職者に離職票を渡す
ハローワークから交付された「離職票-1」と「離職票-2」を、退職者に速やかに渡します。
〇2025年1月20日からはマイナポータルでの直接交付サービスも開始。一定の条件を満たせば、離職票が直接退職者のマイナポータルに送付されるため、企業から渡す必要がなくなります。
離職証明書の基本的な書き方
離職証明書は、左側に賃金状況、右側に離職理由を記入します。自己都合退職を例に、主な記入項目を見ていきましょう。
左側の記入項目(賃金状況)
・被保険者期間算定対象期間: 離職日以前の1か月の区切りを記入し、賃金支払基礎日数が11日以上ある月を原則12か月分記入します。
・賃金支払基礎日数: 賃金の基礎となった日数を記入します。有給休暇も1日として含めます。
・賃金額: 賃金形態に合わせて、支払った賃金額を記入します。手当なども漏れなく含めましょう。
右側の記入項目(離職理由)
・離職理由(事業主記入欄): 離職理由に該当する番号に〇をつけます。自己都合退職の場合は「5(2)労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)」を選択します。
・具体的事情記載欄(事業主用): 離職理由を具体的に記入します。自己都合退職の場合は「自己都合による退職」と簡潔に記入します。
まとめ
離職票の手続きは、企業と退職者の双方にとって非常に重要です。特に離職理由の記載は、失業手当に大きく影響するため、必ず退職者と確認・合意を取ってから手続きを進めるようにしましょう。
手続きを円滑に進めることで、退職者との良好な関係を維持し、会社の信頼を守ることにつながります。